スキンケア化粧品の裏事情
~薬事法制に阻まれる科学との対話~
日本では、薬機法が化粧品の定義を定め、表現についても事細かに制限を加えています。これは、誇大広告を抑え、消費者が誤った情報に惑わされないようにするためのものです。しかし、その一方で、真摯な研究開発に取り組む企業にとっては、足かせになっている面も否めません。
本稿では、そのジレンマに焦点を当て、規制のあり方について考えます。

ビタミン、ミネラル、ポリフェノールなど栄養素が豊富です。
カカオ代用品として注目されるキャロブ

カカオ豆の価格高騰が止まらない。したがって、最近のチョコレートは値上げをするか、中身の量を減らすか、の二者択一を迫られています。また、一流サロンで使われるココバタも、カカオを原料としていますので、同様の状況です。そんな中、チョコレート代用品として名乗りを挙げる原料が登場しています。実はその中に、「キャロブ」(別名:イナゴマメ)があることをご存知でしょうか。日本人にはあまり馴染みのない植物です。
地中海原産のキャロブは古くから人々に利用され、キリスト教の聖書にも登場する由緒ある食料です。マメ科の植物ですから、莢の中に豆が入っています。
食用となるのは莢の部分で、その内側には自然な甘味をもつ果肉があります。シロップなどに加工されたり、ミルクと混ぜて飲まれているそうです。種子はとても硬く、直接食べることはできませんが、アイスクリームやゼリーに入っている増粘剤(ローカストビーンガム)用途として大々的に使われています。また、余談ですが、粒の大きさがそろっていることで、当時は分銅としても使われていた、とか。今日、宝石の重さを「カラット」で表示していますが、0.2gを単位としているのは、キャロブ種子の一粒(0.2g)を基準単位にしたからです。
そのキャロブが数十年ぶりに注目されています。冒頭でも紹介した通り、チョコレートの代用です。加工技術が向上し、風味も改良されました。もともと甘いので、砂糖の添加量を抑えられます。さらにキャロブには、食物繊維からビタミン、ミネラル、ポリフェノールなど豊富な栄養素を含み、健康面への評価は高い食材です。長らく家畜の飼料として、そして古来より人類も食してきた歴史をもつキャロブは、安全性に懸念がなく、その応用研究に期待が高まります。

チョコレートの代用として注目のキャロブは、豊富な栄養素を含み、健康面への評価が高い。

さて、このキャロブに着目したのは、私たち新生ナボカルも同じです。海外の大学と提携し、肌への応用研究を進めています。特に注目しているのは、抗酸化物質として化粧品の分野でも期待されているポリフェノールです。緑茶やカカオ由来などもありますが、私たちが選んだのはキャロブです。安全性が高いわりに、研究がまだ不十分な植物で、しかも将来性を感じさせるポテンシャルを秘めています。
当社が提携しているパートナーの報告によると、遺伝子レベルでの働きが示唆されています。ポリフェノールが、特定の遺伝子の発現を促進・抑制・調節したりすることはすでに色々な研究で発表されており、決して突飛な話ではありません。キャロブ由来のポリフェノールが秘める可能性を解き明かすべく、私たちは研究を進めています。
薬機法の下での「いたちごっこ」
日本には薬機法が存在します。化粧品や医薬品の役割を定め、品質を守り、その販売流通に関する秩序を保っています。医薬品の開発には厳格なプロセスが設けられ、その選択や提供には、医者や薬剤師の関与を必要としました。一方、化粧品は、自由度が高い反面、「効果はなくてもいいが副作用は許されない」、というスタンスが採られています。しかし、効果がないと分かっていながら化粧品を購入する消費者はいないでしょう。そのため、メーカー側は、効果を期待させるような宣伝を行い、規制当局との間で「いたちごっこ」を繰り広げる、そんな滑稽な現状があります。
この混乱の原因の一つは、法律の建前と、現実との乖離です。化粧品は、定められた以上の効果を謳ってはいけないことになっています。少なくとも公式には、薬機法(第2条第3項)にて、化粧品が「人体に対する作用が緩和なもの」と定義し、厚労省が具体的なガイドラインを設けています。しかしそれは、清潔や保湿などのシンプルな効果(現在56項目)のみで、効果の程度も限定的と定めています。たとえ論文などで一定の効能を主張できたとしても、宣伝に用いることは許されません。

化粧品業界では、各社が開発競争で互いにしのぎを削り、より効果の高い、「体にいい」製品を生み出そうとしています。民間である限り当然の行為です。しかし、科学的な成果を正確に伝えることさえ規制されてしまう現状は、混乱を招きかねません。ただ規制当局が頭を悩ます理由もよく分かります。何を許し、何を許さないか、恣意的な線引ができないからです。歴史的に受け継がれてきた「民間療法」は特に難しく、広く流布され、定着していながら、必ずしも科学的な証明がなされていないことも多々あります。宣伝としては(厚労省のガイドライン表現以外)一切許さないことを共通のルールとするのが、一番「楽」なのかもしれません。
ただし、薬事法制では、次のことに疑問を感じます。たとえば、「アンチ・エイジング(若返り)」がダメだから、その代わりに「エイジング(加齢)・ケア」を用いる、という「表現NGワードの言い換え」が議論されている現状です。果たして、言い換えたからと言って、何が変わるのでしょうか。「若返り」を真に受ける愚民がいることを政府は本気で心配しているのでしょうか。むしろ本質を見るべきでしょう。
言葉遊びが主流になっている現状を、業界のためになっているとはとても思えません。単語の是非ではなく、表現内容が客観的な情報提供に基づいているのか、根拠のない宣伝色が強いのかで判断されるべきです。
化粧品における成分競争
中国ではコロナ禍以前の数年間、化粧品ブームが到来し、ネットでは日本製の化粧品が大きな人気を博しました。その、インフルエンサーの影響力が高いEC市場において『成分党』と呼ばれる、化粧品の成分にこだわる消費者が台頭し、彼女たちの素人議論が沸騰しています。また同じ時期に、中国政府も、かつての日本のような管理監督体制に改め、化粧品の乱造が起こらないような規制を強化しています。一見すると、中国の化粧品市場は、情報の普及と監督の強化によって、健全な方向に進路を修正したかに見えました。
ところが、中国の『成分党』の人々の議論を聴いていると、あらためて化粧品に関する議論の難しさを痛感させられます。化粧品に含まれる「コンセプト」成分はそれぞれがわずかな比率で配合され、多くの場合、1%にも達しません。このような微量な成分で差別化を図るのは至難の業です。逆に、特定の成分を大胆に配合してしまうと、過去に日本で発生した健康被害を招いてしまう可能性も孕んでしまいます。過去の教訓から、各メーカーは、慎重かつ控えめな処方設計を心がけているのです。したがって、成分党の方々が熱弁するほどの効果は、ほとんどの化粧品には期待できないのが現実です。
真の差別化要因になり得るとするならば、それは新しい成分の発見でしょう。大手化粧品メーカーは研究を地道に重ね、新たな成分の効能を検証するために実験を繰り返しています。この分野の可能性は無限大です。今日、遺伝子解析によって様々な成分が発見されていますが、地球上には、膨大な数の植物種の中に存在しているはずです。遺伝子技術の発達は、この探索作業を効率化するだけでなく、遺伝子レベルでの効能メカニズムの解明においても役立ちます。それは何も医薬品に限った話ではありません。化粧品においても、新しい可能性を切り開く鍵となるのです。

中国の化粧品ECでは『成分党』と呼ばれる、化粧品成分にこだわるインフルエンサーが台頭
真摯な研究と、開かれた対話
この新しい原理を説明しようとすれば、従来の化粧品の枠組みを越えてしまうかもしれません。薬機法コンサルタントは、決まり文句のように言うでしょう:「遺伝子への作用を謳うのは医薬品的な効果を連想させる」、と。しかし、冒頭のキャロブの例で示したように、歴史的に見て人体に安全だとみなされるものが、一定の効果を期待できる場合、その効能研究を客観的に表現できるようになっていてほしいです。
たとえば、コーヒーは、世界中で毎日広く飲用されているものですが、ほぼ毎週のように、その効能や副作用を研究した報告がメディアに取り上げられます。日常的に飲用されつつ、科学との対話を冷静に続けている、とても理想的な姿です。研究が進み、理解が広がり、製品や原料をみんなで改良していく。そんな開かれた対話環境が整っています。化粧品業界でも、そのような風土と法環境を実現し、新たな成果を模索し続けていきたいものです。
最後に触れておきますが、薬機法(旧薬事法)の改正が行われて以降、活発になったはずの商品開発はやや歪な姿になっています。必ずしも研究・実験に立脚したものではなく、むしろ、宣伝やパッケージなどの小手先で差別化を図り、言葉遊びを競っている傾向が見られます。製品の処方がほとんど同じであるにも関わらず、広告で劇的な効果を表現しようとすることに何の意味があるのでしょうか。研究投資を怠り、マーケティング企業とOEM工場の組合せが普及する今日の日本では、薬機法対策の「言い換え」表現に終始している製品がはびこるわけです。
私たちナボカルが目指すのは、キャロブの中に秘められたコラーゲン生成に寄与する成分の発掘と改良です。その成分が、人体に内在するコラーゲン生成のメカニズムに、どのように働きかけられるのか。その研究を深め、化粧品の効果をもう一段高みへと引き上げたい。それが私たちの夢になりました。かつて、宝石の「カラット」の語源ともなったキャロブが、人の体に(宝石のような)どんな素晴らしいプラスを与えてくれるのか、そんな研究報告を、皆さんとの対話にしていけたらと願うばかりです。

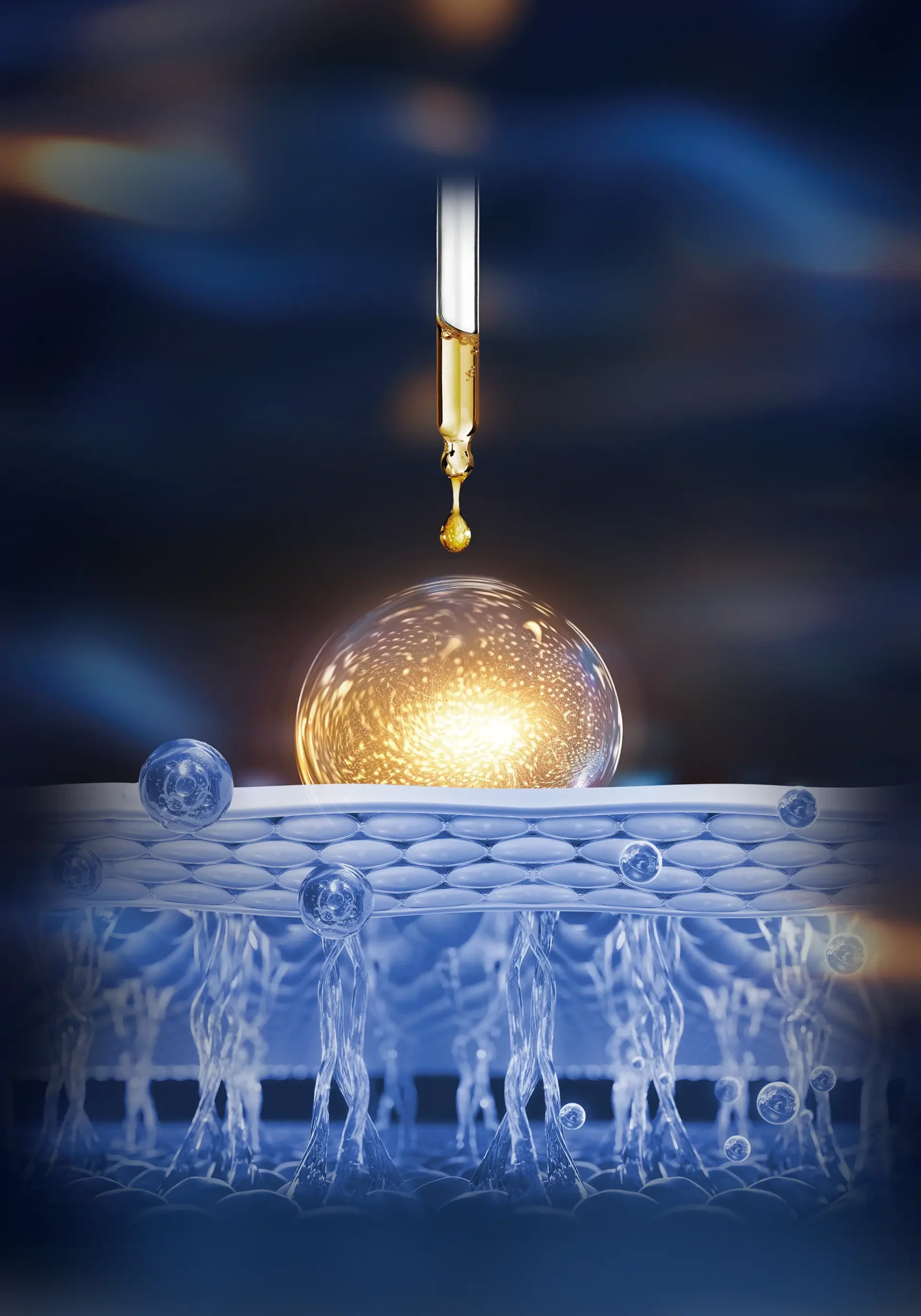
私たちナボカルが目指すのは、キャロブの中に秘められたコラーゲン生成に寄与する成分の発掘と改良です。その成分が、人体に内在するコラーゲン生成のメカニズムに、どのように働きかけられるのか。その研究を深め、化粧品の効果をもう一段高みへと引き上げたい。それが私たちの夢になりました。かつて、宝石の「カラット」の語源ともなったキャロブが、人の体に(宝石のような)どんな素晴らしいプラスを与えてくれるのか、そんな研究報告を、皆さんとの対話にしていけたらと願うばかりです。

キャロブはチョコレートの代用品として注目されており、食物繊維、ビタミン、ミネラル、ポリフェノールなど栄養素が豊富です。
スキンケア
化粧品の裏事情
~薬事法制に阻まれる科学との対話~
日本では、薬機法が化粧品の定義を定め、表現についても事細かに制限を加えています。
これは、誇大広告を抑え、消費者が誤った情報に惑わされないようにするためのものです。
しかし、その一方で、真摯な研究開発に取り組む企業にとっては、足かせになっている面も否めません。
本稿では、そのジレンマに焦点を当て、規制のあり方について考えます。
・・・
カカオ代用品として
注目されるキャロブ
カカオ豆の価格高騰が止まらない。したがって、最近のチョコレートは値上げをするか、中身の量を減らすか、の二者択一を迫られています。また、一流サロンで使われるココバタも、カカオを原料としていますので、同様の状況です。そんな中、チョコレート代用品として名乗りを挙げる原料が登場しています。実はその中に、「キャロブ」(別名:イナゴマメ)があることをご存知でしょうか。日本人にはあまり馴染みのない植物です。
地中海原産のキャロブは古くから人々に利用され、キリスト教の聖書にも登場する由緒ある食料です。マメ科の植物ですから、莢の中に豆が入っています。
食用となるのは莢の部分で、その内側には自然な甘味をもつ果肉があります。シロップなどに加工されたり、ミルクと混ぜて飲まれているそうです。種子はとても硬く、直接食べることはできませんが、アイスクリームやゼリーに入っている増粘剤(ローカストビーンガム)用途として大々的に使われています。また、余談ですが、粒の大きさがそろっていることで、当時は分銅としても使われていた、とか。今日、宝石の重さを「カラット」で表示していますが、0.2gを単位としているのは、キャロブ種子の一粒(0.2g)を基準単位にしたからです。

チョコレートの代用として注目のキャロブは、豊富な栄養素を含み、健康面への評価が高い。
そのキャロブが数十年ぶりに注目されています。冒頭でも紹介した通り、チョコレートの代用です。加工技術が向上し、風味も改良されました。もともと甘いので、砂糖の添加量を抑えられます。さらにキャロブには、食物繊維からビタミン、ミネラル、ポリフェノールなど豊富な栄養素を含み、健康面への評価は高い食材です。長らく家畜の飼料として、そして古来より人類も食してきた歴史をもつキャロブは、安全性に懸念がなく、その応用研究に期待が高まります。
さて、このキャロブに着目したのは、私たち新生ナボカルも同じです。海外の大学と提携し、肌への応用研究を進めています。特に注目しているのは、抗酸化物質として化粧品の分野でも期待されているポリフェノールです。緑茶やカカオ由来などもありますが、私たちが選んだのはキャロブです。安全性が高いわりに、研究がまだ不十分な植物で、しかも将来性を感じさせるポテンシャルを秘めています。
当社が提携しているパートナーの報告によると、遺伝子レベルでの働きが示唆されています。ポリフェノールが、特定の遺伝子の発現を促進・抑制・調節したりすることはすでに色々な研究で発表されており、決して突飛な話ではありません。キャロブ由来のポリフェノールが秘める可能性を解き明かすべく、私たちは研究を進めています。

薬機法の下での
「いたちごっこ」
日本には薬機法が存在します。化粧品や医薬品の役割を定め、品質を守り、その販売流通に関する秩序を保っています。医薬品の開発には厳格なプロセスが設けられ、その選択や提供には、医者や薬剤師の関与を必要としました。一方、化粧品は、自由度が高い反面、「効果はなくてもいいが副作用は許されない」、というスタンスが採られています。しかし、効果がないと分かっていながら化粧品を購入する消費者はいないでしょう。そのため、メーカー側は、効果を期待させるような宣伝を行い、規制当局との間で「いたちごっこ」を繰り広げる、そんな滑稽な現状があります。

この混乱の原因の一つは、法律の建前と、現実との乖離です。化粧品は、定められた以上の効果を謳ってはいけないことになっています。少なくとも公式には、薬機法(第2条第3項)にて、化粧品が「人体に対する作用が緩和なもの」と定義し、厚労省が具体的なガイドラインを設けています。しかしそれは、清潔や保湿などのシンプルな効果(現在56項目)のみで、効果の程度も限定的と定めています。たとえ論文などで一定の効能を主張できたとしても、宣伝に用いることは許されません。
化粧品業界では、各社が開発競争で互いにしのぎを削り、より効果の高い、「体にいい」製品を生み出そうとしています。民間である限り当然の行為です。しかし、科学的な成果を正確に伝えることさえ規制されてしまう現状は、混乱を招きかねません。ただ規制当局が頭を悩ます理由もよく分かります。何を許し、何を許さないか、恣意的な線引ができないからです。歴史的に受け継がれてきた「民間療法」は特に難しく、広く流布され、定着していながら、必ずしも科学的な証明がなされていないことも多々あります。宣伝としては(厚労省のガイドライン表現以外)一切許さないことを共通のルールとするのが、一番「楽」なのかもしれません。
ただし、薬事法制では、次のことに疑問を感じます。たとえば、「アンチ・エイジング(若返り)」がダメだから、その代わりに「エイジング(加齢)・ケア」を用いる、という「表現NGワードの言い換え」が議論されている現状です。果たして、言い換えたからと言って、何が変わるのでしょうか。「若返り」を真に受ける愚民がいることを政府は本気で心配しているのでしょうか。むしろ本質を見るべきでしょう。
言葉遊びが主流になっている現状を、業界のためになっているとはとても思えません。単語の是非ではなく、表現内容が客観的な情報提供に基づいているのか、根拠のない宣伝色が強いのかで判断されるべきです。
化粧品における成分競争
中国ではコロナ禍以前の数年間、化粧品ブームが到来し、ネットでは日本製の化粧品が大きな人気を博しました。その、インフルエンサーの影響力が高いEC市場において『成分党』と呼ばれる、化粧品の成分にこだわる消費者が台頭し、彼女たちの素人議論が沸騰しています。また同じ時期に、中国政府も、かつての日本のような管理監督体制に改め、化粧品の乱造が起こらないような規制を強化しています。一見すると、中国の化粧品市場は、情報の普及と監督の強化によって、健全な方向に進路を修正したかに見えました。
ところが、中国の『成分党』の人々の議論を聴いていると、あらためて化粧品に関する議論の難しさを痛感させられます。化粧品に含まれる「コンセプト」成分はそれぞれがわずかな比率で配合され、多くの場合、1%にも達しません。このような微量な成分で差別化を図るのは至難の業です。逆に、特定の成分を大胆に配合してしまうと、過去に日本で発生した健康被害を招いてしまう可能性も孕んでしまいます。過去の教訓から、各メーカーは、慎重かつ控えめな処方設計を心がけているのです。したがって、成分党の方々が熱弁するほどの効果は、ほとんどの化粧品には期待できないのが現実です。
真の差別化要因になり得るとするならば、それは新しい成分の発見でしょう。大手化粧品メーカーは研究を地道に重ね、新たな成分の効能を検証するために実験を繰り返しています。この分野の可能性は無限大です。今日、遺伝子解析によって様々な成分が発見されていますが、地球上には、膨大な数の植物種の中に存在しているはずです。遺伝子技術の発達は、この探索作業を効率化するだけでなく、遺伝子レベルでの効能メカニズムの解明においても役立ちます。それは何も医薬品に限った話ではありません。化粧品においても、新しい可能性を切り開く鍵となるのです。

中国の化粧品ECでは『成分党』と呼ばれる、化粧品成分にこだわるインフルエンサーが台頭
真摯な研究と、
開かれた対話
この新しい原理を説明しようとすれば、従来の化粧品の枠組みを越えてしまうかもしれません。薬機法コンサルタントは、決まり文句のように言うでしょう:「遺伝子への作用を謳うのは医薬品的な効果を連想させる」、と。しかし、冒頭のキャロブの例で示したように、歴史的に見て人体に安全だとみなされるものが、一定の効果を期待できる場合、その効能研究を客観的に表現できるようになっていてほしいです。
たとえば、コーヒーは、世界中で毎日広く飲用されているものですが、ほぼ毎週のように、その効能や副作用を研究した報告がメディアに取り上げられます。日常的に飲用されつつ、科学との対話を冷静に続けている、とても理想的な姿です。研究が進み、理解が広がり、製品や原料をみんなで改良していく。そんな開かれた対話環境が整っています。化粧品業界でも、そのような風土と法環境を実現し、新たな成果を模索し続けていきたいものです。
最後に触れておきますが、薬機法(旧薬事法)の改正が行われて以降、活発になったはずの商品開発はやや歪な姿になっています。必ずしも研究・実験に立脚したものではなく、むしろ、宣伝やパッケージなどの小手先で差別化を図り、言葉遊びを競っている傾向が見られます。製品の処方がほとんど同じであるにも関わらず、広告で劇的な効果を表現しようとすることに何の意味があるのでしょうか。研究投資を怠り、マーケティング企業とOEM工場の組合せが普及する今日の日本では、薬機法対策の「言い換え」表現に終始している製品がはびこるわけです。
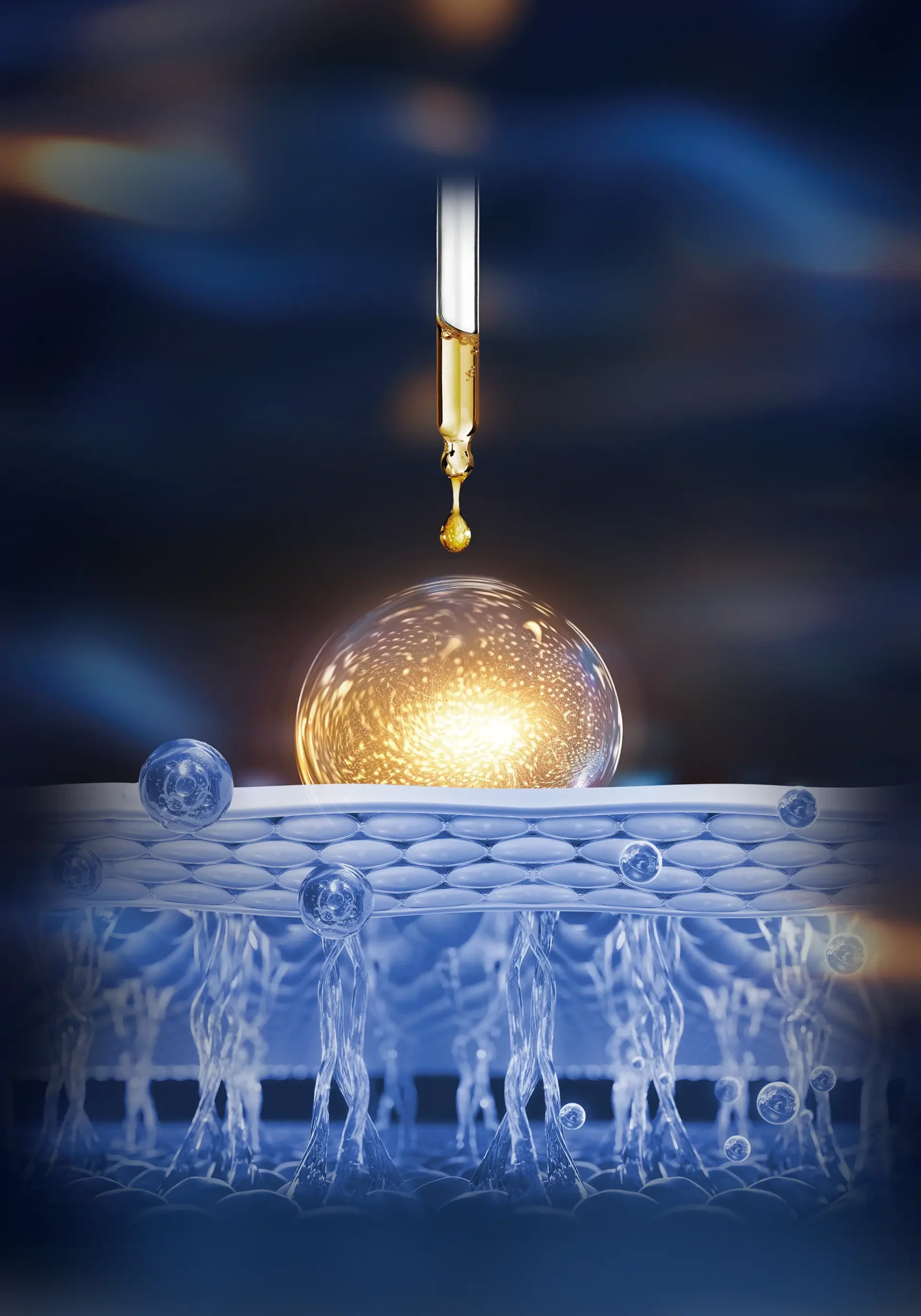
私たちナボカルが目指すのは、キャロブの中に秘められたコラーゲン生成に寄与する成分の発掘と改良です。その成分が、人体に内在するコラーゲン生成のメカニズムに、どのように働きかけられるのか。その研究を深め、化粧品の効果をもう一段高みへと引き上げたい。それが私たちの夢になりました。かつて、宝石の「カラット」の語源ともなったキャロブが、人の体に(宝石のような)どんな素晴らしいプラスを与えてくれるのか、そんな研究報告を、皆さんとの対話にしていけたらと願うばかりです。
